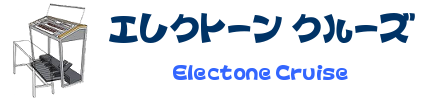タッチトーンの歴史
ピアノでの表現力は、演奏もさることながら、
微妙なタッチで音に変化をつけられる
ことが大きい。これは、楽器一般的に言えることだ。音の起点に強弱をつけたり、音が鳴っている間に音自体に変化を加えることができる。
エレクトーンはどうであろうか?基本的には、

geralt / Pixabay
単純に言うと、鍵盤というのは、
音を鳴らすスイッチ
のようなものでしかなかった。その歴史を変えてきたのがタッチトーンの技術であり、FS/FX時代から本格的に導入されてきた。
タッチトーンの種類
音色が変化するのは大きく分けて2種類ある。一つは減衰音、打楽器のように、発音したらそのまま消えていく音、もう一つは金管楽器のような持続的な音がある。
初期の段階では、
減衰音のグループと
持続音のグループ
に分けてタッチトーンがかけられた。
イニシャルタッチトーン
減衰音のグループにかけられるようになった機能で、弾いたときの強弱によって、音の大きさや音色を変化させる。ピアノをはじめとして、打楽器系の音色群に使用可能となった。
アフタータッチトーン
持続的な音のグループにかけられるようになった機能で、弾いている鍵盤をさらに下へ押し込むことで、音の大きくしたり、音色を変化させたりする。イニシャルタッチのグループ以外の音色群に使用することができた。
次世代の音色の変化
90年以降のモデル、EL世代に入ると
イニシャルタッチとアフタータッチは各音色それぞれに設定できる
ようになった。また、その深度なども細かく設定できるようになる。上鍵盤でバイオリンとフルートの音色を使用している際に、バイオリンにアフタータッチ、フルートにイニシャルタッチをかけるという選択もできるわけだ。

CMEPinky / Pixabay
同時に、ビブラートもかけられるようになっているのだが、これを設定以外にもアフタータッチで自在にかけられるようにすることも可能だ。ただし、タッチビブラートとアフタータッチは、当然別々にすることもできない。となれば、別々にするしかない、というのは普通の発想だ。縦方向だけではなく、横に揺らして表現するという方法を取り入れるのは、EL第二世代からのことである。
まとめ
オルガンから発生したエレクトーンは、当初は選んだ音を鍵盤に従って出力するだけのものでした。それに、音量の調節や弾き方の変化によって、演奏の表現力が加わります。本物の楽器にどこまで近づくことが必要なのかは定かではありませんが、やはり、せっかく音を出すからには、
本物に近い音色、表現力ができるように
なるのはよいことでしょう。
最新のELS-02シリーズでは、
ピアノの音など、かなりクオリティも高く
なってきていますので、未知の世界の方は、一度、ヤマハに足を運んでみるのもよいかと思います。